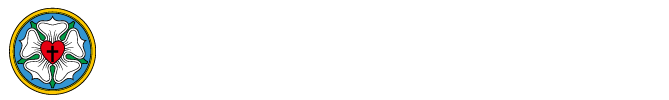復活後第3主日(4月23日)「心が燃えた」
 二人は、「道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」と語り合った。 ルカによる福音書24:32
二人は、「道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」と語り合った。 ルカによる福音書24:32
【説教要旨】 「心が燃える」
復活されたイエスさまと夢破れて、意気消沈し、自分の故郷へ帰る弟子の出会いの大変に有名なエマオ途上の物語です。私たちも人生の途上にあり、夢破れて、意気消沈し、自分の故郷へ帰るという状況に置かれるときもあるでしょう。そういう時も24:15 話し合い論じ合っていると、イエス御自身が近づいて来て、一緒に歩き始められたとありますようにイエス御自身が近づいて来て、一緒に歩き始められるのです。それが私たち信仰者の人生の旅です。私たちは一人ではない。近づいてきてくださるると感じる人生の旅があるのです。
24:16 しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったとあります。あれほど親しくイエスさまと接していた弟子が気づかなかったことはおかしいと思いませんか。ルカは、「二人の目は遮られていて、」と説明しています。森一弘司祭は、「イエスの姿にすばやく気がついてもよかったはずなのですが、外見から見抜くことができなかったのです。ということは、その外見が、必ずしも生前のイエスの姿そのままではなかったということになります。」と言われています。
 宮田光雄先生は、レンブラントの「エマオの晩餐(1645年)」の説明で次のように言われています。「とくに興味深い一枚の素描が『エマオの晩餐』(1645年)がある。弟子たちが主を認めた瞬間に、それまでイエスの座っていた椅子の人影は消え、その代わりに輝きわたる光が目に入るばかりである。この輝く光によってのみ象徴された復活のキリストは、もはや描写することのできない信仰体験を暗示するものです」
宮田光雄先生は、レンブラントの「エマオの晩餐(1645年)」の説明で次のように言われています。「とくに興味深い一枚の素描が『エマオの晩餐』(1645年)がある。弟子たちが主を認めた瞬間に、それまでイエスの座っていた椅子の人影は消え、その代わりに輝きわたる光が目に入るばかりである。この輝く光によってのみ象徴された復活のキリストは、もはや描写することのできない信仰体験を暗示するものです」
-1-
「24:31 すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。」
森一弘司祭は、この出来事をレンブラントの同じ様にもはや描写することのできない信仰体験として次のように言っています。 「外見から見抜くことができなかったのです。ということは、その外見が、必ずしも生前のイエスの姿そのままではなかったということになります。
しかし、やがて、弟子たちは、その外見はどうあれ、イエスのよびかけ、説明、動作を通して、それがイエスであること、生前、師として慕っていた方そのものであることに目覚めていきます。生前、自分たちと共に歩み、人々に説教し、奇跡を行い、十字架につけられていったあのイエスが、そこに、自分たちの前に、死後も現存し、語りかけてくることを理解していくのです。 生前のイエスと同じイエスが、十字架の死の後も、復活体となって弟子たちに働きかけてくれるということ、ここに奇跡があるのです」。
これを復活の神秘、宮田先生によると輝く光によってのみ象徴された復活のキリストは、もはや描写することのできない信仰体験だということです。
復活の命に私たちが生かされていこうとするためにイエス御自身が近づいて来て、一緒に歩き始められ、復活は神秘に与らせていただけるのです。復活の命の神秘にいかされることこそ、「道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」。
復活のイエス・キリストとの対話の中で、心をイエス・キリストに向かわしめるのです。それも心は燃えるのです。
-2-
私たちの信仰の生活においても、私たちの傍らに立ち、歩んでおられるイエス・キリストに目を開かれるくことが大切ではないでしょうか。また、私たちの信仰生活とは「いつもイエス・キリストに目を開かれる」という日々ではないでしょうか。
遠藤周作さんは、「決定的に何かがそこに加わらなければ、弟子たちは結束して、信仰に燃え、多くの異邦人の国々に旅する筈はないのだ。決定的な何かが加わらなければ、あれほどの師について理解少なかった弟子たちが本当の教えを知る筈はないのだ」といって、生きたイエスに出会ったことにある。復活にあるというのです。神が働く、ここに私たちが復活の力をいただき心が燃えていく。私たちが何よりも神の働きを強く信じ、信頼していくことです。イエス・キリストに目を開かれていくことです。若松英輔氏は、遠藤周作さんの「深い河」の解説で、「復活をめぐる事実として、何よりも重大なのは、復活のイエスを経験した誰もが、かつて肉体をもって生きていたイエスに劣らないほど近く、確かにその存在を感じ得ていることなのです。・・・・・・・・先に見たように師イエスの死を契機に弟子たちは変貌します。ただ、弟子たちは自分一人で新しい道を歩いていると感じたことはなかったと思います。大津がそうだったように、目に見えない姿をしたイエスが、いつも寄り添っている、そう感じたように思うのです。」といっているように
一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かった
私たちも旅の途上にあります。その途上にあって、イエス・キリストが見えるところは、今、私たちがいるここ、礼拝の場です。ここから神の働きを受け、心が燃やされ、神の愛を証しするものとして旅立てるのです。「永遠の命を得」と教会の正面に刻んだエルソン牧師らがイエスに寄添われながら心燃えて宣教した歴史がここにあり、私たちの歴史であり、信仰の旅を続けていきましょう。
★「愛とゆるしと祈りと」 森一弘 中央出版 ★「いのちの証人たち」 宮田光雄 岩波書店 ◆「日本人にとってキリスト教とは何か」若松英輔 NHK出版新書
-3-
 牧師室の小窓からのぞいてみると
牧師室の小窓からのぞいてみると
復活日以降、教会は春の墓前礼拝を行う。教区主催の小平霊園、今日は横浜墓地である。私たちの大森教会は、5月に初代エルソン牧師を偲び横浜外人墓地で墓前礼拝を行う。
碑文谷創さんの一文に「葬式は個人を悼み、家族、友人ら自分を支えてくれる人との縁を確認する場だと。人は弔い、弔われる。最期のときまでに、どんな縁が結べるか。時に『メメント・モリ(死を思え)』と口ずさみ、有限の人生を慈しみたい」とある。
しかし、コロナ感染以降、縁を確認する場が取られ、縮小した。葬儀が変貌した。
そして新たな時が来ている。「人は弔い、弔われる。最期のときまでに、どんな縁が結べるか。時に『メメント・モリ(死を思え)』と口ずさみ、有限の人生を慈しむ」という生きた日々が縁を確かめる日々であり、葬儀の時ではなくなった。生きている時が全てであるという凄まじい荒々しい時代が今のようである。
墓前礼拝は、そういう荒々しく生きている私たちにもう一度、ゆっくりと縁を確かめる癒しの時だと感じている。今こそ、墓の前で手を合わせることが大切ではないだろうか。
 園長・瞑想?迷走記
園長・瞑想?迷走記
入学式、進級式、春の遠足と春が早く過ぎて行くように時間が過ぎていきました。
いつものように時は動き出したように見えましたが、いつもと違うことも起きています。遠足の時いつものように楠の樹の下で日差しを避けました。新型コロナ感染の3年間で楠は大きく成長し、いつもより手を大きく広げて私たちを守ってくださいました。いつもと違う新しい園のドラマは始まったと感じる一瞬でした。
-4-
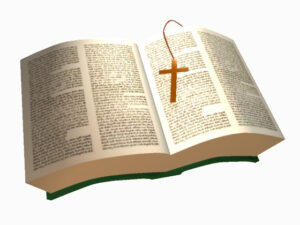 日毎の糧
日毎の糧
聖書: 私の時は、御手の中にあります。 詩編31:15
 ルターの言葉から
ルターの言葉から
もし、神が、私たちに死後の命を見せてくださるか、または、私 たちの魂が、どこへ踏み出し足を下ろすか、どこへ立ち去ってとどまることになっていうか、その場所や期間、過程や方法を示してくださるとしたら、死は苦いものではなく、両岸に頑丈な足場が見えており触れることもできる浅瀬の上を飛び越えるようなものである。
『慰めと励ましの言葉 マルティン・ルターによる一日一生』 湯川郁子訳 徳善義和監修 教文館
時
「この詩人に強く感得せしめたものは思うに時である。従って時がこの詩人において非常に重要な意義をもっていると思われる。」と浅野順一先生は言い、最も決定的な時は神に出会う時であると言い。「この詩人は如上の意味において時を正しく理解し、それがすべての神の手にあることを体験的に感得し、それによって彼は暗黒の室から光明の部屋に移されることが出来た。それ故詩人にとって時は運命とか宿命とか言うべきものではなく摂理である。それは『破れた器』のごとき絶望の状態に陥る時にも、なお光を全く失わず、希望の回復を忍耐して待ち、やがて、勝利の確信にまで導かれて行くものであることをこの詩は強く教えている」(「詩篇」 浅野順一 岩波新書)
私たちが生きる時は、神の御手にあると信じ、信頼することこそ、神の摂理、慈愛の中で生かされていることに気づきます。
月本氏が、「本詩全体をヤハウェの『慈悲』(8,17,22節)と詠い手の「信頼」(7,15節)という神学的視点からまとめあげている。そこから『わが霊を御手にゆだねます』(6節)『わが時は御手の中です』(16節)といった、本詩に独特な深い信頼の言葉が紡ぎだされたのである。」というように私たちも独特な深い信頼の言葉が紡ぎだす私たちの時を今週も暮らしていきましょう。
祈り:神への深い信頼をもって私の時を紡ぐことができますように。
-5-
 大森通信 大森通信
「引退の準備」 伝道45年 総会資料Ⅺ 「牧会Ⅵ」 教会成長の三原則、1.みことば-ベテル聖研2 継続は金なり ベテル聖研が大森教会でも行われたが、継続しなかった。これは大森教会だけではない。教会には継続性がない。リーダーである牧師が7・7・7の21年制度で退任していくのも癌だと思うが、よく、「牧師が変わっても教会の伝道は変わりません。」というが、教会の信徒がよっぽどしっかりして伝道をしなければ、継続性がなくなる。 吉本隆明氏が面白いことを言っている。 「いつも言うことですが、結局、靴屋さんでも作家でも同じで、10年やれば誰でも一丁前になるんです。だから、10年やればいいんですよ。 他に特別やらなきゃならないことなんか、何もないからね。10年間やれば、とにかく一丁前だって、こうこれは保証してもいい。100%ものになるって、言い切ります。 ただし、10年やらなかったら、まあ、どんな天才的な人でもダメだって思ったほうがいいってふうにも言えるわけです。9年8ケ月じゃダメだって(笑)。」 家内のオルガン奏楽をみていると、最初は教会学校の奏楽者がなく、主旋律のみだった。次にブラジルに行くと奏楽者がいないから二旋律、慣れてきて三旋律、帰国してオルガニストに恵まれていたので夕礼拝のみ。大森で奏楽し始め、先生につき、四旋律になった。10年どころか40数年の継続(笑)。 |
 (大森日記)土)雨。休みの雨と感謝。日)新学期でミッションスクールの子が多くやってくる。午後は教区主催小平霊園での墓前礼拝。コロナ下で会えなかった方々と会える喜びもあった。アカペラで夕礼拝。月)几帳面な家内にカード紛失という事件。互いに老いた。火)いつものように身辺整理。水)オンライン会議、2件続けて。木)聖書の学び、癒される。玄関口を夜、掃除。金)幼稚園の遠足。いつもなら金曜日まで仕上げている礼拝準備が出来ず寝る。引退最後までもつか不安。
(大森日記)土)雨。休みの雨と感謝。日)新学期でミッションスクールの子が多くやってくる。午後は教区主催小平霊園での墓前礼拝。コロナ下で会えなかった方々と会える喜びもあった。アカペラで夕礼拝。月)几帳面な家内にカード紛失という事件。互いに老いた。火)いつものように身辺整理。水)オンライン会議、2件続けて。木)聖書の学び、癒される。玄関口を夜、掃除。金)幼稚園の遠足。いつもなら金曜日まで仕上げている礼拝準備が出来ず寝る。引退最後までもつか不安。